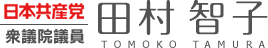(写真)質問する田村智子議員=5日、参院内閣委
日本共産党の田村智子議員は5日の参院内閣委員会で、「パチンコ・パチスロの規制をしなければギャンブル依存症の防止対策はまったく不十分になる」として、パチンコの換金システムである「3店方式」への規制を強く要求しました。
田村氏は、刑法犯の動機に占めるギャンブル・パチンコ依存のそれぞれの件数をただしました。警察庁の山下史雄生活安全局長はパチンコ以外のギャンブルに起因するものは1182件、パチンコに起因するものは1388件(2017年)だと明らかにしました。
田村氏は「パチンコへののめり込みのために日々深刻な事件が生じている」と指摘。パチンコで行われている脱法的な換金行為をなぜ規制しないのかただしました。
山下局長は「パチンコの景品を第三者が買い取ることはただちに違法とはならない」と答弁。田村氏は「警察がパチンコの換金システムを守っているのと同じだ。パチンコ・パチスロへの対策を国家公安委員長の出席のもとで審議すべきだ」と求めました。
田村氏は「パチンコ・パチスロ規制として今すぐできることがある」として、パチンコ店内に設置されている銀行ATM(現金自動預払機)の撤去を要求。金融庁の松尾元信参事官は「金融機関による取り組みをモニタリングしていく」と銀行まかせの姿勢をとりました。
田村氏は、教育現場での依存症対策は「賭博は犯罪であるということ、『やらない』ことが大切だと教えなければ、依存症対策にはならない」と指摘。「カジノを解禁するなど、本当にありえない」とのべました。
3店方式 パチンコ店が客から景品を直接買い取る換金行為は風俗営業適正化法で禁じられています。このため(1)客が「パチンコ店」で出玉を特殊な景品と交換(2)特殊景品を店外の「景品買取所」で換金(3)特殊景品は「問屋」を通じてパチンコ店に戻る―という3店を循環させる方式での脱法的な換金行為が広く行われています。
2018年7月6日(金)しんぶん赤旗より
【7月5日 参議院内閣委員会議事録】
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
ギャンブル依存症の対策は大きく二つの柱が必要だと考えます。一つは、依存症になってしまった人への対策。医療や社会的支援、家族、特に子供への支援策なども本当に求められるというふうに思います。そしてもう一つは、新たな依存症を生まないための対策です。依存症になってしまった人への対策は緒に就いたばかり、新たな依存症を生まないための対策は更に遅れているということを私は三日の参考人質疑で痛感いたしました。
そこで、衆法、参法の提出者それぞれにお聞きいたします。
新たな依存症を生まないというために、賭博そのものであるカジノを合法化することはあり得ないというふうに私は考えますが、意見をお聞かせください。また、それぞれが提案しているギャンブル依存症対策はカジノ実施を前提としたものであるのかどうか、お答えください。
○衆議院議員(岩屋毅君) 先生が指摘をされましたのはIR整備法のことだと思いますけれども、御案内のとおり、これは一昨年の暮れに成立をいたしましたIR推進法の第五条に基づいて講じられる法制上の措置でございます。本来ですと昨年のうちに国会に提出されていなければいけなかったということだと思いますが、解散・総選挙等がございましたので、作業が遅れていると承知をしています。
IR整備法の是非についてはその整備法の御審議の中で是非ただしていただきたいというふうに存じますが、政府においてギャンブル依存症を防止するための重層的かつ多段階の措置が講じられていると承知をしています。
一方、私ども、今度提案をしておりますこの法案は、IRとは切り離して議論されるべきという観点から、ギャンブル等依存症に対する国民の不安や懸念の声に応えるために立案をしたものでございます。やがて、仮にIR整備法が成立をいたしまして、その施設の中に含まれるカジノが開業した場合には本法案の対象になっていくわけでございますが、IR整備法にビルトインされている仕組み、そしてこの基本法に基づいて行われる対策が総合的に講じられることによって、我が国におけるギャンブル依存症の全体的な状況が改善するものと期待をしているところでございます。
○委員以外の議員(小西洋之君) お答え申し上げます。
私は、昨年なんですけれども、民進党時代でありますが、この依存症対策の法案の担当チームの事務局長として韓国の江原ランドを視察してまいりました。そこで、カジノによる依存症の実態、そのギャンブル場の経営者、また自治体の職員の方も言っていましたけれども、カジノによる依存症の効果というのは非常に大きいものがあると。山奥の炭鉱跡の場所に造られているものなんですが、三百万人を超える韓国の国民がソウルから専用バスに乗ってやってくると、そのような実態を見ました。
それで、委員御指摘の新たな依存症を生まないということに着目したときに、新たなカジノによる依存症を生まないためにはカジノそのものをつくらないということは、因果関係としてはそれは明らかであろうと言えると思います。
その上で、本法案の立法趣旨でございますけれども、まさに御指摘のパチンコなどを始めとして世界でも有数のギャンブル依存症の言わば大国になっているこの現状で、国民の生命、また家族の幸せ等々、そうした大問題に、危機にとにかく対処するためにこの法案は立法したものでございまして、カジノの実施を前提にしたものではございません。
なお、私、無所属の、立憲民主党・民友会の所属の議員でございますが、衆議院の審議におきましては、立憲民主党の発議者の方から、カジノを解禁することによって新たな依存症者が増加する、依存症対策を進めていく上で新たな依存者が増加するようなことを進めるべきではないという見解を述べた上で、IR推進法の廃止法案の提出、これは御党とも共同提出でございますけれども、そのような言及がなされているところでございます。
○田村智子君 続いて、衆法案、ギャンブル等依存症というふうにしていますけれども、この等の中にパチンコ、パチスロが含まれるということなのかどうか、パチンコ、パチスロはギャンブルそのものではないという認識かどうか、お聞かせください。
○衆議院議員(中谷元君) この法律の第二条のギャンブル等は、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為と規定をいたしております。したがいまして、等は風営法の範囲で行われる遊技が該当するものでございます。
○田村智子君 一方、参法の方は、ギャンブル依存症対策というふうに、等はないわけですね。これは、パチンコ、パチスロをギャンブルとみなしているのかどうか。また、ギャンブル依存症の防止のための対策を進める上で、事実上の換金システムである三店方式なども含め、パチンコ、パチスロに規制の検討が必要という認識をお持ちかどうか、お聞かせください。
○委員以外の議員(小西洋之君) お答え申し上げます。
本法案では、公営競技やパチンコのみならず、違法な賭博も含めまして広くギャンブル依存症対策を推進する観点から、あえてギャンブルという用語の定義、これは置かずに、ギャンブル依存症の定義を置いたところでございます。パチンコ、パチスロを原因とする依存症についても、公営競技等によるものと同様にこの対策の中で対策が講じられていくこととなります。その意味で、この法律の定義の限りにおいて、ギャンブル依存症のギャンブルにはパチンコ、パチスロが含まれております。
このような整理は、ギャンブル依存症という用語の報道機関等々での用いられ方、あるいはパチンコ、パチスロを原因とするギャンブル依存症の問題、存在に関する一般国民の認識とも沿うものだというふうに考えております。
その上で、本法案でございますけれども、第十七条の第一項におきまして、ギャンブル関連事業者の事業の方法がギャンブル依存症の発生等の防止に配慮されたものとなるようにするために必要な施策を講じる、国や地方公共団体が施策を講じるというふうに規定をしております。
仮にでございますけれども、仮に委員の御指摘が、パチンコ業界のいわゆる三店方式とギャンブル依存症との間には何らかの因果関係があるのではないかというような御指摘であるのでありましたら、そうした御指摘はほかにも社会的にあることは私承知しておりますけれども、政府においてそうした御指摘も真摯に受け止めて、必要に応じてしかるべき調査等はなすべきではないかというふうに考えているところでございます。
○田村智子君 これは、カジノを前提にすることは論外なんですけれども、パチンコ、パチスロの規制を不問にしたら、ギャンブル依存症の対策、特に防止対策は全く不十分なものになってしまうと思います。
そこで、警察庁にお聞きします。
刑法犯罪の動機がギャンブル依存である件数、同じくパチンコ依存である件数、直近の数字でそれぞれ示してください。
○政府参考人(山下史雄君) 犯罪は様々な要因によって発生するものでございまして、これを一概に申し上げることは困難でございますが、警察庁の犯罪統計によれば、平成二十九年中に検挙をした刑法犯約三十二万件のうち、主たる被疑者の犯行の動機、原因がギャンブルをするための金欲しさ等ギャンブルをすることへの欲求であるものの件数は千百八十二件、パチンコ遊技をするための金欲しさ等パチンコ遊技をすることへの欲求であるものの件数は千三百八十八件でございます。
○田村智子君 これ、パチンコ依存が原因とされるものの方が多いわけですね。検挙に至らない事案でも、家族などへの暴力も含め、パチンコにのめり込んだがために日々深刻な事件が生じていると言わざるを得ません。それでも、パチンコはゲームセンターなどと同じ遊技という扱いなんですね。
ゲーム依存症について、WHOによって国際的に疾患と認定をされました。確かに、子供たちも含めて日常生活に支障が出るほどのめり込んでしまう、あるいは課金に対する支払が膨らみ過ぎるなど深刻な事例は日本でも問題になっていますが、これは、親のクレジットカード使っちゃってある月の請求が物すごく増えちゃったと、これで大体発覚して、その月の請求どうするんだというような事例が多いと思うんですよ。
パチンコ依存症の深刻さは次元が違います。うそにうそを重ねて、家族も友人も巻き込んで借金をする、家族に暴力まで振るう、あるいは強盗などの凶暴犯罪にまでつながっていく。ギャンブル依存症の原因となるギャンブルは圧倒的にパチンコ、パチスロであるということはもう分かっていることなんですよね。遊技でありながら他の公営ギャンブルよりも多くの被害者がいる。ゲームとの最大の違いは、お金をするということだけではなくて出玉やコインを簡単に現金化できること、それが多くの被害を生み出しているのではないかと当然に考えますが、警察庁の見解をお聞かせください。
○政府参考人(山下史雄君) 犯罪は様々な要因によって発生するものでございまして、これを一概に申し上げることは困難であると認識をしてございますが、一般にパチンコへの依存問題を抱える方がいることは承知をしておりますし、今ほど御答弁を申し上げたとおり、このパチンコ遊技をするための金欲しさ等パチンコ遊技をすることへの欲求であると、こういったものが被疑者の犯行動機、原因となっている件数が一定あるということは承知をしているところでございます。
いずれにいたしましても、このパチンコへの依存防止につきましては大変重要なものであるというふうに思ってございます。重要性に鑑みまして、昨年八月に関係閣僚会議において決定をされたギャンブル等依存症対策の強化についてなどを踏まえ推進しているところでございまして、今後とも関係行政機関と連携をしつつ、この依存防止対策、パチンコへの依存防止対策をしっかりと推進してまいりたいと考えております。
○田村智子君 答弁かみ合っていないんですけど、ちょっと先に進みますね。
パチンコにはやっぱり換金システムがあると、だからこれほどの深刻な被害があるんだということは、これはもう誰だって分かっていることだと思いますよ。
そこでお聞きしたいんですけれども、換金に関わって検挙された件数、このパチンコで換金に関わって検挙された件数、その事案の説明、主なものをお願いします。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコ営業者が客に提供した賞品を買い取るなどして風営適正化法第二十三条第一項違反として検挙された件数は、平成二十九年中で四件でございます。具体的な事例を申し上げますと、例えばパチンコ営業所の従業員が賞品買取り業務に従事するなど、パチンコ営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品買取りを行っていたものがございます。
○田村智子君 これは、パチンコのお店と景品交換所と言われるところの経営者が一緒だった、これで検挙された事例がある。また、事前のレクでお聞きしましたところ、景品交換所で働く方がパチンコ店の従業員と重なっていたと、これも検挙された事例としてあるんだということもお聞きをしているところなんですけれども。
これ、お客さんはパチンコの出玉に応じて景品を受け取る、多くはパチンコのすぐそばにある景品交換所で景品を現金化する、景品交換所は買い取った景品をまたパチンコ店に売ると、いわゆる三店方式ですね。これは、経営者や従業員がパチンコ店と景品交換所で同一だったら風営法違反、これまでもそれで摘発された事例というのがあると。その理由としては、これは賭博になりかねず、善良な風俗を害するとして禁止されているんだという説明も警察庁から受けました。しかし、これ、通常行われている三店方式と外形的には何ら変わらないと思うんですよ、外から見たとき。お客さんが景品交換所へ行ってお金に換える、それで持っていかれた景品がまたパチンコ店に戻る、これ、外形的に何にも変わらないですよ。にもかかわらず、この景品交換所が何の規制も受けていない。なぜなんですか。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコ営業に係る賞品の買取りにつきましては、風営適正化法におきまして、パチンコ店の営業者が現金等を賞品として提供をすることや客に提供した賞品を買い取ることを禁止をしているところでございます。パチンコ店の営業者以外の第三者が賞品を買い取ることにつきましては、直ちに風営適正化法違反となるものではないというふうに認識をしております。
今ほど先生の方からいわゆる三店方式によるこういったものをもっと規制すべきではないかという御趣旨のお尋ねがございましたが、風営適正化法はパチンコ営業につきまして必要な規制を行うものであるところ、仮にパチンコ店の営業者以外の第三者による買取りを規制することとした場合、一般的な物の売買にまで際限なく規制の対象が広がることとなり、過剰な規制となりかねないものであると考えております。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、パチンコ営業者と実質的に同一であると認められる者が賞品を買い取るなどの違法行為につきましては、引き続き厳正な取締りを行っていく所存でございます。
○田村智子君 それじゃ、お聞きしますが、景品交換所は古物営業に当たるのではないですか。
○政府参考人(山下史雄君) お尋ねのいわゆるパチンコの賞品買取り所につきましては、古物営業の許可を取得する必要はございません。
○田村智子君 今、パチンコの景品の中には有名ブランドのバッグとかがあるそうなんですね。じゃ、その有名ブランドのバッグをパチンコの賞品として受け取りました。それをブランド品売買をするお店で換金をしました。その買い取ったお店はそのブランド品を販売しました。このお店は古物営業法の対象になるんじゃないですか。
○政府参考人(山下史雄君) 今ほど古物営業の許可を取得する必要がないと御答弁申し上げましたが、その理由でございますが、古物営業法が、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務につきまして必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする、この趣旨に鑑みますれば、窃盗等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないパチンコの賞品につきましては、当該パチンコの賞品を買い取ることについて、そもそも古物営業法の規制を及ぼす必要は認められないと考えてございます。
今ほど先生御指摘の例えば一般のブランドバッグでございますれば、盗品等の処分の実態が認められますこと等から、当該物品を買い取ることにつきましては古物営業の許可を取得する必要があると考えているところでございます。
○田村智子君 今の御答弁だと、じゃ、賞品買取り所というんでしょうか、景品交換所というんですか、これはもうパチンコとワンセットという判断ということでよろしいんですか。
○政府参考人(山下史雄君) 今ほど御答弁申し上げましたのは、窃盗等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないパチンコの賞品、これにつきまして、第三者が当該賞品を買い取ることにつきまして古物営業法の規制を及ぼす必要があるかどうかということで御答弁申し上げたものでございます。
○田村智子君 だから、だから、パチンコで受け取ったものだからという理由でしかないじゃないですか。
ブランド買取り店のところに、これはパチンコで受け取ったんだと、パチンコ店から証明書をもらったんだと、そういうブランド品だけ買い取りますよというお店があったら古物営業法の対象にならないということになるんですか。
○政府参考人(山下史雄君) これも今ほど御答弁申し上げましたように、御指摘のような一般のブランドバッグということでございますれば、盗品等の処分の実態というものが認められるところでございます。こういった物品を買い取ることにつきましては、古物営業法の許可を取得する必要があると考えているところでございます。
○田村智子君 そうすると、パチンコ店が出すいわゆる特殊景品は、景品交換所で交換がされ、それがパチンコ店に還流するというシステムがあるから古物営業法には当たらないということになるわけですよね。まさに景品交換所はパチンコの換金システムと言っているのと同じだというふうに思いますよ。全く説明になっていないですよ。
結局、古物営業法の規制対象にすると。だって、ならないのおかしいですよ、古物なんだから。本人がもらったものを処分するというのは、これはもう古物の対象になるわけでしょう。フリーマーケットで売ったってそうなるわけでしょう。それを買い取るとやったら、買取りに来た業者は古物営業法の対象になってくるわけですよ。それを古物営業法の規制にも当たらないと言うと。それは、古物営業法の規制対象にすると景品換金をするときに身分証明などが求められてしまう、そうした規制も掛からないようにするために古物営業法の対象外としているとしか説明のしようがないわけですよね。
パチンコ店が直接客から賞品を買い取った場合も、賭博罪ではなく風営法違反なんですよ、さっきのも。検挙例の中に、景品を出しました、その景品をパチンコ店がお金に換えましたと、これも賭博罪で検挙していないんですよ。風営法違反の検挙というふうになっているわけですよね。
私は、これでは、警察がパチンコ、パチスロの換金システムを守っていると同じだと言わざるを得ないと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコ営業につきましては、その態様によっては客の射幸心を著しくそそることとなるなど、善良な風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあることから、風営適正化法に基づき必要な規制が行われているところでございます。
警察といたしましては、業界に対しまして、射幸性の抑制、依存防止対策等の指導をしているほか、違法行為につきましては厳正な取締りを行っているところでございます。
○田村智子君 やはり政府参考人では駄目ですよ。これ、議論にならないです。
ギャンブル依存症対策でパチンコ、パチスロへの対策を審議しないということはあり得ない。是非、国家公安委員長に御出席いただいて、改めて審議をお願いしたいと思います。委員長、取り計らいをお願いします。
○委員長(柘植芳文君) ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議をいたします。
○田村智子君 パチンコ、パチスロの規制として今すぐできることもあるはずです。簡単にお金がつぎ込める、ここに歯止めを掛けることです。
今、一台一台の機械にお札の投入口があって、パチンコ玉を取りに行く必要もないわけですね。これでは頭を冷やす間も与えないと。これ、出玉規制などは、機械について、警察庁関与しているんですよ、出玉規制については。だったら、すぐにお金がつぎ込めるというこの構造も私は規制すべきだと思いますが、いかがでしょう。
○政府参考人(山下史雄君) 今ほど先生の御指摘ございました営業所内におきまして遊技料金を支払うための現金投入口の場所につきましては、風営適正化法上規制があるものではございませんけれども、客の利用実態あるいは社会的な認識等について警察としても注視をしてまいりたいと思ってございます。
いずれにいたしましても、パチンコへの依存防止対策は重要な課題であると認識をしております。業界におきましても、本人、家族申告による遊技の制限、依存問題を抱える人等への相談対応等の取組が実施をされており、引き続き、各種取組を総合的に推進し、依存問題を抱え不幸な状況に陥る人をなくすための対策を、関係省庁とも連携をしつつ、しっかりと講じてまいります。
○田村智子君 これ、機械については、警察庁関与できるんですから、是非お願いしたいと思います。
金融庁にもお聞きしたいんですね。
負けて熱くなったと、ところが財布開けたらもうお金もなかったと、入れられなかった、そうしたらすぐにお金を下ろすことができる、これも駄目だと思うんですよ。パチンコ店に設置されたATMの撤去、必要だと思います。
現在、ATMの設置は、設置場所を所管する者との協議が調えば自由に行えちゃうんですね。そのため、金融庁は、パチンコ店へのATM設置については業界の自主ルール策定を見守るという姿勢です。
しかし、ギャンブル依存症対策を本気で進めるつもりならば、被害を防止するためにも法令上の規制は行うべきです。せめて、法令上の規制も辞さないぞという厳しい姿勢でルール作りを先導すべきだと思いますが、金融庁、いかがでしょうか。
○政府参考人(松尾元信君) お答え申し上げます。
公営施設やパチンコ店に設置されている銀行ATMにつきましては、公営企業内については平成二十九年度末までにATMのキャッシング機能の廃止、またATM自体の撤去を行うということになっておりまして、また、パチンコホール内についてはキャッシング機能を廃止しているといった取組が行われていると承知しております。
ギャンブル等依存防止は重要な課題であり、このほかにも、全銀協で、全国銀行協会で検討しておりますギャンブル等依存症等を理由とする申告を受けた場合の貸付自粛制度が平成三十年度中を目途に開始されるようしっかりと促していくとともに、ギャンブル等依存症に関連する多重債務問題についての相談対策のマニュアルを作成するなど、専門機関と多重債務者相談窓口との連携を強化するといった取組も行っております。
金融庁といたしましては、金融機関による取組について、ギャンブル等依存症対策の観点から、関係省庁と連携しつつ、モニタリングしてまいりたいと考えております。
○田村智子君 これ、依存症の深刻さ、やっぱり理解していないと思うんですよ。せめて所持金なくなったらもうパチンコ店から出ると、それぐらいのことやらないでどうするのかというふうに思いますよ。
衆法の提案者に次の点をお聞きしたいんですけど、第十四条で、国及び地方公共団体は、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場におけるギャンブル等依存症問題に関する教育及び学習の振興のために必要な施策を講ずるとしていますが、一体どのような教育を行うことを想定しているのでしょうか。賭博は犯罪であり、やってはならないということをちゃんと教えるのか、カジノやパチンコ、パチスロについていかように教育するのか、どうお考えですか。
○衆議院議員(佐藤茂樹君) 今、田村委員の方から十四条についての御質問がございました。この十四条の教育の振興、家庭、学校、職場、地域、そのほかの様々な場におけるギャンブル等依存症問題に関する教育の重要性を規定しております。
家庭における施策というのは、例えば保護者向けの啓発資料を作成し周知を図り、未成年者のギャンブル等へのアクセスの防止を図ることを想定しております。職場における施策というのは、事業者が従業員に対し、ストレスの対処法などギャンブル等依存症の予防等に関する教育指導を行うことを想定しております。地域における施策とは、例えば地域の公民館においてギャンブル等依存症対策に関する講座を実施すること等を想定しております。
田村委員の一番聞きたいのは、教育という場においてどうするのかということであろうかと思うんですけれども、これは本当に、学校における教育というのは、ギャンブル等依存症を予防するに当たっては成人する前の段階における教育が極めて重要であるという観点から、子供の発達段階に応じてギャンブル等依存症関連問題の防止に関する教育や周知を図ること等を想定しております。例えば、パチンコ等に関しては、十八歳未満の者をパチンコ営業所に客として立ち入らせることは法律で禁止されているところであって、こうした禁止行為を正しく認識してもらうことは当然と考えております。
その上で、我々、この法案作成の過程にも、今、政府の方が、学校教育においてはこれまで指導要領等にギャンブル等依存症についての記述がなくて直接的な指導がなされてこなかったと承知しております。昨年の八月に、政府の方としても初めて、高等学校指導要領解説保健体育編において精神疾患の一つとしてギャンブル等依存症を記載することとされているわけでございまして、今その解説本が作成中だというようにお聞きしております。我々もその作成段階のものをしっかりと目を届けさせていただいて、注視してまいりたいと思っております。
子供の発達段階に応じまして、仮に将来ギャンブル等を行うことがあるとしても、依存症のリスクに注意することができるような教育が行われることを我々提案者としては期待しております。
以上でございます。
○田村智子君 これ、文科省にお聞きしたいんですが、薬物依存やたばこについて中学や高校で既に教えていると思います。どのように教えることを基本としているのか、お願いします。
○政府参考人(白間竜一郎君) お答え申し上げます。
先生御指摘のように、喫煙、また薬物乱用防止についての指導については、小学校から高校まで、学習指導要領に基づきまして、体育科、保健体育科を中心に行われております。
今、中高ということでしたので中と高の具体例を申し上げますけれども、具体的に中学校では、たばこにつきまして、たばこの煙の中には有害物質が含まれていること、常習的な喫煙によりがんや心臓病など様々な病気を起こしやすくなることや、未成年の喫煙については依存症になりやすいこと、また高等学校では、喫煙は生活習慣病の要因となり健康に影響があること、周囲の人々や胎児への影響があることなど、受動喫煙の害とともに喫煙の健康への影響について指導が行われているというところでございます。
また、薬物乱用につきましては、中学校で覚醒剤や大麻を取り上げまして、摂取によって幻覚を伴った激しい急性の錯乱状態や急死などを引き起こすこと、薬物の連用により依存症状が現れ、中断すると精神や身体に苦痛を感じるようになるなどの様々な障害が起きる、また高等学校では、コカイン、MDMAなどの麻薬、覚醒剤、大麻など薬物の乱用は、心身の健康、社会の安全などに対して様々な影響を及ぼすので決して行ってはならないことなど、薬物の健康への影響について指導が行われている、そういう状況でございます。
○田村智子君 これ、基本的にはやらないということを教えているはずなんですよ。たばこは吸わない、薬物はもちろん違法ですからやらないと、そうやって学校教育やっているはずなんですね。
基本政策を担当することになる内閣府にもお聞きします。
依存症の実態とともに、やっぱりギャンブル依存症の場合も、賭博は犯罪であるんだと、やらないということを基本に教える、こうしなければ依存症対策の教育にはならないというふうに思いますが、いかがでしょう。
○政府参考人(中川真君) 御答弁申し上げます。
ギャンブル等依存症対策につきましては、政府は関係閣僚会議を立ち上げまして昨年の八月にはこの依存症対策の強化策を取りまとめ、実施可能な施策を順次施行に移していっているという状況でございます。
それで、今の教育、啓発の在り方でございますけれども、これまで発議者からの御答弁、そしてただいま文科省からも答弁がございましたように、まず、子供が成長して大人になった際に、ギャンブルなどに依存せず、これはもしかすると薬物とかアルコールも含めて、こういう依存に陥ることなく自律的に健康的に生きていけるように、学校教育の場では、先ほど御紹介もありましたように、学習指導要領などで新たな精神疾患の一つに位置付けて記載をして教育現場での取組を推進していくという形で取り組んでいるものだというふうに考えてございます。
また、学校教育だけではなくて、ギャンブルの依存のリスクを注意喚起するための取組も、施行者ですとかあるいは事業者による取組としては、インターネット投票サイトですとか、ポスター、リーフレットを活用した注意喚起、普及啓発などが実施されているところでございますし、また、国民誰もがギャンブル等依存になり得るという可能性があることに鑑みますと、依存症は適切な治療や支援により回復可能であることが理解されることが大事だと思っておりますし、そういうことを強調する普及啓発イベントの実施やリーフレットの配布など、既にこの取組を進めているところでございます。
以上でございます。
○田村智子君 これ、予防教育としては極めて心配になるような御答弁だったと。依存症にならないようにギャンブルをやりましょうというような教育になるんじゃないかと、ちょっと危機感を抱くような御答弁だったというように思うんですね。
先日の参考人質疑で、久里浜医療センターの樋口院長に、ギャンブル依存症の予防策としてギャンブルについての正しい知識の教育が必要だという意見陳述があったので、それはどういうものかという質問をいたしました。そうすると、様々なギャンブルについて当たる確率がどれだけ小さいかということを学ぶという例示とともに、それが予防策になるのかはいまだエビデンスがないというお答えだったんですね。
この当たる確率のことというのは、認知行動療法で、現に依存症の患者さんに、こんなに確率が低いのに当たりが出るとあなたは信じていたのよと、こうやって分からせていく、そして次の行動のコントロールに、何というか、きっかけを与えていく、こういう意味では、私、意味があると思います。実際、久里浜医療センターはそういう治療を行っています。
しかし、予防策にはならないでしょう。依存症というのは、千分の一だろうが一万分の一だろうが、一を当てたからのめり込んでいくというわけで、まさに予防策、そのための教育というのは未確立だと言わざるを得ません。それでいてカジノまで解禁するというのは本当にあり得ないということは強調しておきます。
厚生労働省に来ていただきました。
このギャンブル依存症になってしまった方への支援策、診療報酬が低いんじゃないかという問題提起があるんです。
久里浜医療病院も、お一人の方、初診で診るときには二時間、三時間必要になるというんですね。これ、薬も使うわけじゃないですよ。それから、何か手術のような処置が必要でもない。こういう問診のようなものは一番診療報酬が付かないんです。
これ、ちゃんと医療機関がギャンブル依存症を含めた依存症に対応できるように診療報酬大きく引き上げていくこと必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。
いわゆるギャンブル依存症に対する治療に関しまして、診療報酬におきましては、先生から御指摘ございましたように、精神疾患に対する専門的な治療である精神科専門療法として評価をしております。この精神科専門療法に関しまして、今年四月の診療報酬改定におきまして、診療報酬の対象となる精神疾患の定義を最新の国際疾病分類、これWHOが決めておりますけれども、これに即して見直して、ギャンブル依存症につきましても対象疾患であるということをしっかり明確化いたしました。
さらに、ギャンブル依存症につきましては、現在、AMED、日本医療研究開発機構などでの研究が進められておりまして、今後、こうした治療法の開発に関する研究、あるいは治療の安全性、有効性、こうしたものもよく把握しながら、関係者の意見も聞いて中央社会保険医療協議会の場で適切に評価してまいりたいと、このように考えております。
○田村智子君 久里浜医療センターは、実際に持ち出しだと言っています。赤字になってしまうというふうに言っていますので、ここはちゃんと手当てしないと医療機関は増えていかないということは強調しておきます。
もう時間になってしまいましたので、その他、回復施設への公的支援というのもほとんどない状態で、大変多額の費用を負担できる人でなければ回復施設に入居ができない問題などもあります。
是非、そうした支援策への十分な予算措置が行われるよう求めまして、質問を終わります。