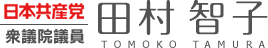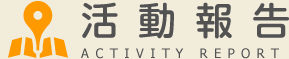被爆80年の8月6日を前に、「日本はどのように核軍縮を主導するか」をテーマに「核兵器廃絶日本NGO連絡会」と「核兵器をなくす日本キャンペーン」共催の討論会が5日、広島市内で開かれました。被爆者や与野党8党の代表、有識者らが参加し、日本共産党から田村智子委員長が発言しました。
田村氏は、被爆80年を契機に日本が果たすべき役割は核兵器禁止条約の批准であり、「核抑止力」論の克服が必要だと強調。「被爆者がヒロシマ・ナガサキの地獄を告発し続けた『人道的アプローチ』が、核兵器禁止条約を誕生させた。『核抑止力』論を乗り越える大きな力になる」と指摘しました。
日本政府が進める核を含む「拡大抑止」や大軍拡について「東アジアにおける核軍縮と安全保障にとって逆流だ」と批判。東南アジア諸国連合(ASEAN)が主導する東アジアサミットの枠組みを活用・発展させ軍縮を求める外交に力を注ぐよう訴えました。
日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の田中熙巳(てるみ)代表委員は「日本政府は核禁条約への参加に決意し、具体的に前進してほしい」と訴えました。
国連の中満泉軍縮担当上級代表は、非核兵器保有国でも「核共有」論が高まり、分断が強まっていると指摘。来年は核不拡散条約(NPT)と核兵器禁止条約の再検討会議があり「日本政府もオブザーバー参加を検討してほしい」と語りました。
オーストリア外務省のアレクサンダー・クメント軍縮局長は、「核抑止」はさまざまな条件がそろうことを前提にしており、「仮定にすぎない」と批判。「核抑止」の克服を強く求めました。
核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)のメリッサ・パーク事務局長は「(核禁条約締約国会議への)日本の不在は多くの方に失望を与えている。『核の傘』への依存は持続可能ではない」と訴えました。
「核共有」や「核武装」を唱える議員を抱える参政党、日本保守党は討論会に出席しませんでした。
被爆80年機に核禁条約批准を/田村委員長の発言/NGO討論会/要旨
日本が果たすべき役割は被爆80年の今年、核兵器禁止条約の批准に向けて動くことです。そのために「核抑止力」論の克服が求められています。
核兵器の非人道性への告発が重要です。被爆者のみなさんは、ヒロシマ・ナガサキの地獄を告発し続け、この「人道的アプローチ」が、核兵器禁止条約を誕生させました。「人道的アプローチ」こそが、いざとなれば核兵器を使うことを前提とする「核抑止力」論を乗り越える大きな力であり、被爆証言を私たちも受け継いで力を尽くしたいと思います。
日本政府も、核兵器の非人道性を認めています。しかし、わが党が「いかなる状況のもとでも核兵器の使用は許されない」という立場をとるのかと国会でただすと、答弁を逃げて、「安全保障環境の厳しさ」を言い訳に「核抑止力」論に固執しています。
この点で、核兵器禁止条約第3回締約国会議の報告書が、抑止のほころびという「安全保障上のリスク」を指摘し、「核兵器は、すべての国家の安全に対する深刻かつ根本的な脅威」であると明記したことは、とても重要だと考えます。
ぜひ核不拡散条約(NPT)および禁止条約の再検討会議に向け、「核抑止力」論を打ち破る議論を日本国内でも広げていきたいと思います。
日本政府が進める、拡大抑止や大軍拡は、東アジアにおける核軍縮と安全保障にとっての逆流だと指摘しなければなりません。
わが党は、東南アジア諸国連合(ASEAN)と協力して東アジアを戦争の心配のない地域にする平和構想を提唱し、国内外で行動しています。その立場は、「軍事ではなく対話」「排除ではなく包摂」です。
中国との関係が一つの焦点ですが、日中両国は「互いに脅威とならない」ことを合意しており、この合意にもとづく行動を双方がとるべきです。わが党はこのことを中国に直接提起し、中国側も「日本共産党の提起を重視している」との回答を得ています。
こうした対話を2国間だけでなく、ASEANと協力し、東アジアサミットという現にある枠組みを活用・発展させる、これが紛争の平和的解決への具体的で現実的な外交につながっていきます。軍拡から軍縮への転換を、東アジアサミットなどを活用して進めることを求めていきます。
2025年8月6日(水) しんぶん赤旗